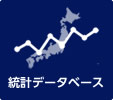騎手のセカンドキャリアに向けた支援(イギリス)【開催・運営】
それは不安が渦巻くなか、内密に始まった。問い質された出席者が関与を否定するような会合が密かに行われ、その構想が浮かび上がった。30年が経ち、それは競馬界になくてはならない存在として定着した。懸命に働く騎手の士気を高めるための拠り所となり騎手を取り巻く環境の改革の象徴となったのだ。
それがJETS、つまり騎手教育訓練計画(Jockeys' Education & Training Scheme: JETS)である。多くの騎手は「その日」を迎えて、検量室をあとにすると、もう何もすることがない。この制度は、競馬界で繰り返されてきたこのような悲哀に対処すべく作られたものなのだ。
「キャリアが終盤に近づいたとき、多くの騎手が戦々恐々としていることが浮き彫りになりました」とマイケル・コーフィールド氏は語る。同氏は1988年に英国騎手協会のCEOに就任した。当時はいくつもの分野に改善が急務とされていた時代だった。ストランズオブゴールドがヘネシーゴールドCで勝利した週に任命された同氏が、同馬に騎乗した障害競走のチャンピオン・ジョッキーであるピーター・スクダモア氏から受けた最初の指令は、シンプルだが切実なものだった。「なんとかしてくれ!」
職務の一環として、コーフィールド氏は負傷騎手基金(Injured Jockeys Fund: IJF)の会議にたびたび出席していた。同基金の評議員らは、支援を必要としている元騎手から寄せられた援助申請を検討していた。
「毎回、議案に挙がっていた大きな懸念事項は、元騎手が心から好きだった仕事や騎乗から離れたのち、何のあてもなく暮らしているということでした」とコーフィールド氏は振り返る。「言うまでもなく、元騎手のほとんどは金銭的に安定していませんでした。何らかの故障を抱え、十分な蓄えもなく、若くして学業から離れたため、職業訓練も受けていないのです。「第二の人生」に向けて準備をしてもらうために、スキルを身に付けさせてあげることさえできればと考えていたことを覚えています」。
コーフィールド氏は「第二の人生」という言葉を使って、騎手がレースでの騎乗を止めたあとの人生を表現していた。元騎手に対して「引退」という言葉を使うことを禁じたのだ。30歳や35歳で本当に人生を引退する人なんていない。元騎手たちには別の何かが必要だったのだ。
同じころ、平地競走の検量室でも元騎手のダナ・メラー氏は同じ現象に気付いていた。
「明らかに次のステージに進みたがっているのに、その方法が分からず、焦燥感を募らせた騎手をたくさん見ました」と同氏は話す。「住宅ローンも残っているし、養う家族もいるのです。でも、何から手を付けたらいいのか分からず、ただ騎乗を続けるしかなかったのです」。
簡単な道などない。スターターや裁決書記といった競馬界の花形ポストには元軍人が充てられることが多い。元騎手がこうした職務に就くこともあったが、理想的な人材群としては見られていなかった。また、正直なところ、騎手自身たちですら、そう思っていなかったのだ。
メラー氏は「当時、あちこちでよく耳にしたのは『自分は馬に乗ることしかできない。他のことは何もできない』という言葉でした」と振り返る。
「自信をなくしている騎手の姿を目の当たりにしてきました」とコーフィールド氏は話す。「キャリアも終盤に迫ってきて、頼れるものもなく、することが何もないのです」。鞍を置くということは社会的地位と人生の目的を瞬時に失うことを意味した。「電話は鳴らなくなり、馬券予想に使える情報を聞きに来る人もいなくなって、エージェントに電話をかけることも無くなると、世界が全く違うものになってしまうのです」。
元騎手たちのこういった鬱々とした思いは、スリルを与えてくれるものがなくなってしまうという現実に追い打ちをかけるものだった。向こう見ずな2歳馬に騎乗して疾走することもなければ、コントロールの利かない障害未勝利馬を連続する障害に向かわせることもない。これ以上に楽しいものなんて見つからないのだ。
1990年代前半のある時点で、IJFは支援対象である元騎手にアンケートを実施した。何が一番の支援になるのか?最も求められていることは何なのか?圧倒的多数の回答が「仕事」だった。
そのため、「競馬就業支援」と呼ばれる試験的な制度を創設した。負傷中にボランティアとしてIJFにかかわっていたメラー氏が、この制度の運用を任された。プロ騎手になる前に法学部を卒業しており、競馬界にも精通している同氏の経歴がふさわしいものだったからだ。同氏の父スタン・メラー氏は、障害競走で初めて1,000勝を遂げた騎手だ。のちに調教師となり、チェルトナム・フェスティバルで勝利を収めた。母のエレイン・メラー氏は20年にわたるキャリアで最多勝女性騎手に7度も輝いた。
コーフィールド氏は、騎乗を止めた後のセカンドキャリア形成を目的として、組織的で資金に裏打ちされた訓練プログラムを構築するという案に会員の支持を取り付けるため、奔走していた。「忘れられない日があります」と、同氏はノースヨークムーアズのほとり、ストークスリーにあるIJF福祉担当者の自宅で開いた初期の会合を思い出す。
英国北部をベースとする騎手の大物が集まっていた。コーフィールド氏の記憶が正しければ、そこにはコリン・ホーキンス氏、クリス・グラント氏、ジョン・ロウ氏、マーク・バーチ氏、マーク・ドワイヤー氏が出席していた。関与を否定できるよう秘密裏に行われた会合だった。議題は作られず、議事録も取られなかった。
「全員、ひどく神経質になっていました」とコーフィールド氏は語る。「カーテンを閉め切ったIJF担当者の自宅ダイニングルームで行いました。誰かに見られるのを心底、恐れていたのです。経理や馬の歯科技工の講座など、第二の人生のために準備をしていることを知られたら、どの調教師からも、もう騎手を辞める気なのだ。度胸がなくなったのだと思われると考えていたようです」。
最終的には、コーフィールド氏が、再訓練のための基金として騎手の賞金から一定の割合を充当するという案に、苦労して過半数の支持を取り付けた。IJFからは同額の助成金が上乗せされた。こうして、JETSは1995年にメラー氏を運営責任者に迎えて、スタートしたのだ。
それでも、懸念を払拭するには至らなかった。メラー氏は「賛成に投票した騎手の中にも、電話をかけてきて『自分が支援を受けていることを誰にも言わないでほしい。引退するつもりだなんて思われたくない』と話すのです」と振り返る。
「本当にデリケートな問題でした。騎乗に100%集中すること以外、何かをするつもりだと口にするのはタブーだったのです。キャリア形成という概念そのものが存在していなかったのです」。
しかし、それが今では当然のものとなった。制度開始当初に人気があったのはメディア訓練講座だった。数十年後の現在では、ファンが楽しんでいるテレビ中継スタイルをJETSが形作ったのだ。メラー氏は、ルーク・ハーヴィー氏、ジェイソン・ウィーバー氏、ミック・フィッツジェラルド氏、アンドリュー・ソーントン氏といった90年代の検量室を彩った面々で熱心だった参加者を思い起こす。
フィッツジェラルド氏はJETSへ率直に感謝の念を示す。
「JETSが訓練を開始した際にメディアコースを受講し、大きな助けになりました」とフィッツジェラルド氏は語る。「昔は、馬から降りた後の人生を考えるなんて許されない風潮がありました。近ごろでは、第二の人生を準備するために騎手が自由に活用できる素晴らしい支援があります」。
メラー氏自身もキャリアアドバイザーの資格を取得したため、どんな職種が合っているのか、よく分からない騎手にアドバイスすることができた。同氏は、次のキャリアを決定する際に騎手が示す対照的な二つの考えに注目していたことを思い出す。
「『どんな形であれ、競馬界に残りたい。競馬から離れることはできない』という人もいれば、『騎手でいられず、検量室に居場所がないのなら、競馬には近づかないし、一切関わりたくない』という人もいます」。
「肉体的な痛みを伴います。本当に痛むのです。以前は主役だったのに、今はただ一人の観客なのですから。父のスタンが調教を止めたとき、そばで見ていた私ですら耐え難いものがありました」。
しかし、実際には騎手が騎乗以外にも幅広い職種で活躍できることが分かった。コーフィールド氏はJETS卒業生に「エンジニア、科学者、大型トラック運転手」がいると振り返る。
調教場周辺にいると、他の職業に就いている卒業生と出会うこともあるかもしれない。読者のみなさんもニューマーケット時計台の近くにあるエヴァ・モスクロップ氏のカフェ「コルタード」に立ち寄ったことがあるだろう。ストウ・オン・ザ・ウォルドに昔からあるイアン・シューマーク氏の「グリーディーズ」でフィッシュアンドチップスを買ったことがある読者もいるのではないだろうか。この店では自ら鞍にまたがるようになるずっと前のコナーとキーランのシューマーク兄弟を目にしたことがあったかもしれない。
時にセカンドキャリアにも、ギリギリの危うさが必要なことがある。競走馬に乗るのを楽しんでいたタイプの人間が穏やかな生活に満足できるのはまれだ。リスクを恐れない性格は、クリス・ウェブ氏が自動車教習所の教官としてキャリアをスタートさせる際には間違いなく助けとなった。17歳の若者と同乗し、車のハンドルを握らせても動じないのだ。
こういったことから、一部の元騎手がサイレンとともに街中を駆け巡ることになるのも必然だった。カイリー・マンサー=ベインズ氏はロンドン消防署の一員となった。トーマス・ブラウン氏はイングランド東部救急車サービスにて救急救命士への道を歩んでいる。ブラウン氏は「とても充実しています。この仕事をするために生まれてきたのだと思います」と先日、語っていた。
マンサー=ベインズ氏とブラウン氏はともに、年間表彰であるリチャード・デイビス賞の受賞者だ。この賞はJETSが主催しており、新たなキャリアやスキル取得により著しい成果を示した騎手を表彰するものである。賞の名前は、JETSで新たなスキル習得に励んでいた矢先の1996年夏に、27歳の若さで落馬事故により亡くなった騎手リチャード・デイビス氏にちなんでいる。毎年、遺族が授賞式に参加している。
ブラウン氏のほかにノミネートされた元騎手の一人に、ジョシュ・クレイン氏がいた。鞍を置いて、操縦桿を握るためにパイロット免許を取得し、航空会社ジェット2(Jet2)への就職を勝ち取った。また、トマシーナ・"トミー"・エイストン氏は、障害競走の騎乗を続けながら、(優秀な成績で)神経科学の修士号を取得した。騎手にはある種の無謀さが必要とされるのかもしれないが、なかには並外れて頭脳明晰な騎手もいるのだ。
学問の道へ進む際にJETSからサポートを受けたのは、エイガン・コンロン博士だ。フォスラス競馬場にて、レベッカ・カーチス調教師の管理馬で勝利した7ポンド(約3.2キロ)の減量騎手A.コンロンとして覚えている読者もいるかもしれない。今や、サッカー・プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCの選手育成プログラムを担当する心理学者を務めている。
スポーツ心理学という分野に挑戦し他者との差別化を図る手段として、博士号の取得を勧められたことを思い出す。「あの資金援助がなければ、あれだけの額のお金を使おうという覚悟はできなかったでしょう」と語る。
メラー氏がJETSを去ったあと、引き継いだリサ・ディレイニー氏は、マネージャーとして23年間務めたのち、今年9月に退いた。同氏は、就任当初、ある調教師から優秀な人材を競馬界から流出させていると憤りをぶつけられたことを思い出す。JETSが騎手に再訓練を施して、競馬界の別の業務に就けるようにしているのだと反論した。そのうちの誇らしい例として、スチュワーズC勝利騎手であるリチャード・パーハム氏を挙げた。同氏は英国競馬学校で長年、主任教官を務めている。
「従業員を大切にして、いい経験を積めるようにしてあげれば、その業界にとどまってくれるでしょう」と同氏は話す。「騎手も大切にする必要があります。門の外では、競馬界に入りたい人が行列を成して待っているわけではないのです」。
「騎手が騎乗以外のことをしていると、騎手としてのキャリアには興味がないのだろうとされる傾向が未だにあります。次のステージに移ることを考えているのではないのです。ただ、先んじて別の手を準備しているだけなのです」。
2018年にオーストラリアでラグビー選手を対象に実施した研究では、セカンドキャリアの計画を立てることによって、実際にアスリートのパフォーマンスが改善されたとの結果が示された。コーフィールド氏がストークスリーで不安に苛まれていた騎手たちを振り返ってみると、それは30年も前に直感で見抜いていたことだった。「騎乗を止めたあとにも進む道があると分かっていれば、リラックスして騎乗できるので、実際上、騎乗キャリアでも大きな自信を与えてくれるはずです」。
さらに同氏は続ける。「そして、それは実際に起きたのです。騎乗の他にも、実務訓練を積み、専門書を読んで、学ぶことなど、自分には騎乗の他にもできることがあるのだと実感することにより、自分を少しだけ好きになり始めるのです」。
かつて騎手たちが口にしていた「自分には馬に乗ることしかできない」という嘆きは、もはや耳にすることがない。30年にもわたるJETSの活動に敬意を表したい。
By Chris Cook
[Racing Post 2025年12月10日
「'Jockeys would be really terrified' - the group born in secrecy and fear that proved riders can do much more than sit on horses」]