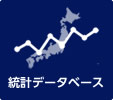日本が23年来抱き続ける凱旋門賞制覇の夢(フランス・日本)【その他】
日本人の凱旋門賞(G1)を勝つことへの"執念"が本格化したのは2006年のことだった。1999年にエルコンドルパサーがモンジューに惜敗を喫するなど、それまでも輝かしくも失敗に終わった企てはあった。だがディープインパクトが凱旋門賞に参戦したとき、熱狂的な興奮が沸き起こった。それは急成長中の競馬国の願望を糧に増大したフラストレーションの産物だった。
数千人ものディープインパクトのファンがロンシャンに現れ、英国やアイルランドから来た常連の観客とは比べものにならないようなやり方で、その場所を我がものとしてしまった。2005年の三冠馬に対する愛情で結束した来訪者たちは、観客席で密集した一団を形成し、礼儀正しく敬意深く振る舞うも、すさまじい熱狂状態にあった。
彼らが大勢で詰めかけたことにより、PMU(フランス場外馬券発売公社)のオッズはすぐに歪みだした。彼らが皆、賭けるという目的ではなくお土産として少額の馬券を"購入"していることが話題となった。その結果、ディープインパクトの単勝オッズは滑稽にも1.1倍に達し、ほかの馬の馬券の売行きは低調になった。プレスルームでは貪欲な記者たちがオッズの不均衡につけ込もうと躍起になって、自らに訪れた運の良さが信じられないという状態となった。一方、PMUのオッズで馬券を売っていた英国のブックメーカーの代表者たちはヘルメットを被って逃げ出した。
フランスの出走直前オッズは1.5倍となり、大スターの武豊騎手がサンデーサイレンス産駒を先頭に立たせると、どんなに滑稽なオッズであってもそれは正しいものであり、"日本人の凱旋門賞優勝への欲求はついに満たさせるのではないか"と思われ始めた。しかしそのリードは勝負を決定的なものにするには十分ではなく、レイルリンク(牡3歳)が外側から長くて苛酷な戦いを仕掛けてくる中、ディープインパクトが勝つには相当な試練が必要なことが明らかになった。
よく統制のとれた日本の競馬ファンは一斉にレースカードを振って声援を送り、武騎手はディープインパクトに力を振りしぼるよう促した。しかし3.5kgの斤量差が十分有利に働いてレイルリンクが優勝し、フランスの牝馬プライドが力強くゴールしてディープインパクトから2着の座を奪い取った。アンドレ・ファーブル調教師とアラン・ド・ロワイエ-デュプレ調教師は遠征してきた池江泰郎調教師から歴史的勝利を奪い、おとぎ話は現実的すぎる地元チームの勝利に転じてしまった。
それでも日本は世界で最も急速に成長する競馬国のままだった。ディープインパクトの敗北はさらなる成長を遂げて願望を強めることの妨げにはならず、凱旋門賞はその願望の中心にあり続けた。ディープインパクトはその敗北のあと日本に帰国し、さらにG1・2勝を挙げ、サラブレッド生産の要となった。
日本の生産プログラムが実を結び始めた
日本がまだ凱旋門賞を勝てない一番の理由は、このレースがフランス・英国・ドイツにとってさえも勝つのが非常に難しいということにある。日本馬がユーラシア大陸を横断する移動をすること、そして比較的経験が不足していることに加え、このレースは欧州でも最もトリッキーなレースの1つであるということだ。
しかし少し視野を広げると、世界で最も急速に成長している競馬国にとって凱旋門賞が決して唯一の目標ではないことははっきりしてきている。このレースで勝てないことがおそらく彼らの挑戦意欲を研ぎ澄ましてしまっているのかもしれないけれど、固定観念は日本人よりも欧州から見ている者のほうにあるのかもしれない。
結局のところ、国際競走たけなわのシーズンに芝競走を施行する多くの国や地域に出向いたことで、凱旋門賞での勝利を犠牲にしているとも考えられる。日本はブリーダーズカップ開催(昨年11月)で2勝、香港国際競走(昨年12月)で2勝、サウジカップ開催日(今年2月)で4勝、ドバイワールドカップナイト(今年3月)で5勝を挙げている。これらの勝利を合計しても、世界を席巻したとは言い切れないかもしれない。しかし、10月のロンシャンにこだわり続けているとされる日本にしては印象的な勝利数である。
凱旋門賞が間近に迫っているので語り口が変わってくるのだが、凱旋門賞の勝利が日本競馬にとって大きな名誉になることは間違いないだろう。ただ1981年にジャパンカップが導入され、競馬の国境が開かれてから、信じられないほどの短期間で大きな進歩があったことは疑いようもない。
かつて日本の高額賞金は、地元チームがまだレベルの低い競走しかしていなかったので、世界のあらゆる国・地域から遠征してくる馬にとって狙い目だった。長期的な影響は徐々に明らかになってきた。ジャパンカップは第17回までで日本馬は5勝しかしなかったが、それ以降の24回(第18回~41回)では22勝している。外国馬で最後に勝利を収めたのは2005年のアルカセット(ルカ・クマーニ厩舎)だ。
この劇的な変化の鍵は、日本の生産者たちがこの目覚まし時計に早くから反応したことである。彼らは世界中からトップクラスの種牡馬候補をすさまじい勢いで輸入した。10年ほどのあいだに外国産馬が日本の最高級レースで勝利を挙げれば、やがて利益を生むだろうと考えていたのだ。そして彼らは、ダービーや凱旋門賞の優勝馬、そしてサンデーサイレンスのようなトップクラスの米国産馬を購買し、それらの素晴らしい競走成績に見合う完璧な血統の牝馬も同時に輸入し、その結果、国内の生産界は一変しだのだ。
吉田ファミリーをはじめとする日本の先駆的な生産者が競馬産業を養い、現在に至っている。なお吉田ファミリーが運営する社台ファームには、現在1,800頭もの繁殖牝馬が繋養されている。
当初、世界中のビッグレースが日本に輸入された競走馬のターゲットになっていた。シーキングザパール・タイキシャトル・アグネスワールドなどがフランスや英国のG1競走を制覇している。しかし一方で、日本の生産計画はその間ずっと実を結んできており、日本のホースマンたちは世界中のレースへの挑戦に向けて馬を仕上げるコツを学んでいた。
そしてついに2012年、2011年の三冠馬オルフェーヴルが欧州最高峰のレース、凱旋門賞で勝利を収めることで長年の投資が報われるとの期待が急激に高まった。
「オルフェーヴルは速すぎて呼吸が乱れていたと思う」
2010年にナカヤマフェスタが凱旋門賞の栄光をつかむべくブローニュの森に到着するころには、エルコンドルパサーやディープインパクトのことは忘れられていたかもしれない。サンデーサイレンスの孫であるナカヤマフェスタ[父ステイゴールド(JPN) 母ディアウィンク(JPN)]はその年の宝塚記念(G1)を制し、フォワ賞(G1)では優勝馬にわずか¾馬身差の2着だったが、凱旋門賞では23倍ものオッズで臨むことになった。そのレースにはフランスとアイルランドが誇るベーカバドとフェイムアンドグローリーが上位人気で出走していた。
このレースでは、上位人気馬が1着~3着を独占することはまずない。二ノ宮敬調教師が管理し蛯名正義騎手が騎乗したナカヤマフェスタは道中順調に走り、直線の入口あたりで衝突されたものの残り2ハロンほどで先頭に立ったとき、日本の凱旋門賞でのスランプはもう終わりかと一瞬思われた。
極東からの遠征馬は気丈に走り続けたが、サー・マイケル・スタウト調教師が管理したダービー馬ワークフォースの気迫にはかなわなかった。残り1ハロンの地点でライアン・ムーア騎手がわずかなリードで先頭に立たせたワークフォースは力を振りしぼって前進して頭差の勝利を決め、その年も日本人が抱いていた夢を終わらせたのだ。
これは日本人が凱旋門賞優勝に最も近づいた瞬間であり、今でもそうあり続けている(ナカヤマフェスタは翌年も挑戦したがデインドリームの11着に終わった)。しかしそれは栄光への近さが「頭」・「首」・「○馬身」という単位でしか測れない場合の話である。議論の幅を広げれば、ナカヤマフェスタを勝利から隔てていたのはほんの頭差だったが、2年後のオルフェーヴルと比べるとそれはとてつもなく大きな差になるのだ。というのも、優勝確実とされていたオルフェーヴルはたどたどしいストライドで不可解な敗者に成り下がるという豹変ぶり見せ、ファンを悶絶させたのだ。彼は日本の願望をかなえるのは簡単だと思われたときに、それを投げ捨てた馬である。そして10年が経って、私たちはこの奇妙な結末を少しも理解できるようになっていない。
ディープインパクトがファンの微笑ましい楽観主義に支えられた優秀で先駆的な挑戦者であったとすれば、オルフェーヴルはさらに6年にわたり国際競馬のコツを学んだうえでの産物だったと言える。フォワ賞で単勝1.9倍の1番人気に支持されて納得のいく勝利を収めたあと、キャメロットに次ぐ2番人気(単勝6倍)で凱旋門賞に臨んだのである。彼は何といっても2011年の三冠馬であり、池江泰寿調教師は凱旋門賞を勝つためには何が必要だったかを理解していた。だから経験を積んで前哨戦に出走したオルフェーヴル(父ステイゴールド 母オリエンタルアート)は草分けとなる勝利をつかむ見込みのある馬だった。
残り2ハロンの地点でこの馬は有力馬から優勝確実な馬に変わった。そのとき凱旋門賞のジグソーパズルの重要な最後の1ピースであるクリストフ・スミヨン騎手は危うい走りを見せていたオルフェーヴルを馬群の外に持ち出し、順調に走らせ、強豪中の強豪をなぎ倒した。そのとき彼は何の苦労もなく前進して先頭に立った。
ライバルたちが後ろに遠ざかるにつれ、危険があるとすればすべて彼の中にあるように思われた。それに思い出してほしい。この馬は母国で3200mのG1競走を制しているので、ファンたちにとってスタミナが心配の種になることはなかった。観客の中にいた日本の代表団の盛り上がりは夢が現実に近づくにつれて最高潮に達した。うまくいかないわけがない。
まあ、何がうまくいかなかったのか誰にもよく分からない。スミヨン騎手でさえも。彼は後にこう言っている。「オルフェーヴルが先頭に立ったとき、日本初の凱旋門賞馬になるに違いないと思っていました。なぜそうならなかったのか、いまだに理解に苦しんでいるのです。残り100mの地点で日本馬が凱旋門賞で勝つ確率がこれほど高かったことはありません。なぜ負けたのか、その理由がよく分かりません」。
オルフェーヴルはレーザー誘導ミサイルのように走っていたが、突然日本酒を飲みすぎた男のようにふらふらになったというのがあからさまな事実である。コースの真ん中を走っていたのに遠くにあった内ラチまで流れ着き、最後は内ラチにぶつかり跳ね返され、チャレンジは潰えてしまった。
ほかの出走馬はオルフェーヴルの最初の獰猛な攻撃ですでに燃え尽きており、まだこの日本馬が勝つように見えた。しかし先頭に立つ馬が脚をなくして絶望に陥っていることを察知したのか、抜け目のないベテラン、オリヴィエ・ペリエ騎手が単勝34倍のソレミアを猛然と追い、この牝馬は最後の1完歩で先頭に立ち、意外な勝利をもぎ取ったのだ。
実況者たちは早めに用意していた"歴史的勝利宣言"を"不可解な敗北への驚き"へ差し替え、エキディア(フランスの競馬チャンネル)のジャンニ・カジュラ氏の「日本人は呪われています」という言葉で中継は締めくくられた。
ペリエ騎手は、タフで勇ましいパートナーとともに2着に入るチャンスがあるとある段階で考えたと告白した。そして日本人に同情したことを認めた。一方、スミヨン騎手は敗れた理由を考えていた。「外に持ち出したとき、彼はあまりにも急いで前に出すぎたのです。速すぎて呼吸が乱れて、おそらく心拍数も上がりすぎたのだと思います。その200m前で出していたパワーを考えると、あんなことになるとは想像もつかなかったです。ひどい瞬間でした」。
オルフェーヴルとスミヨン騎手は翌年の凱旋門賞でも健闘したがトレヴの2着に敗れた。しかし、馬にとっても期待を抱く日本にとっても最大のチャンスを逃したのは2012年だった。
今でも凱旋門賞制覇は夢のまま
10年経っても日本の挑戦者たちは夢をかなえられずにいる。それは毎年10月になると登場する永遠のテーマになっている。競馬新興国から競馬国へと変貌を遂げた日本にとっていつか凱旋門賞での勝利をつかむことは時間の問題であり、今年がその年になるかもしれない。しかし輝かしい失敗もまだ続くといったところだろうか。
昨年はオイシン・マーフィー騎手が乗ったクロノジェネシスがトルカータータッソの7着(ディープボンドは14着)となった。今年は大久保龍志調教師がふたたびディープボンドを送り込み、ステイフーリッシュ(矢作芳人厩舎)やドウデュース(友道康夫厩舎)が加わるが、日本の旗手となるのはタイトルホルダーのようだ。
タイトルホルダー(牡4歳 栗田徹厩舎)は、いずれも阪神で施行された天皇賞(春)(G1 3200m)と宝塚記念(G1 2200m)を制してロンシャンに向けての準備を整えた。現在英国のブック―メーカーはルクセンブルクに次ぐ単勝10倍(4番人気)のオッズをつけている。
はたして、この馬が夢をかなえてくれるのだろうか?栗田調教師はタイトルホルダーをパリに送り出したことだけでも夢がかなったように考えているようだが、この馬から人々の注目をそらすつもりはないだろう。
栗田調教師は9月28日(水)にこう語った。「今年は精神的にも大きく成長し、道中のスピードが上がり、それを長く維持できる馬に進化しました。今年に入るあたりに、オーナーとともに凱旋門賞を夢見るようになりましたが、その時はそれだけでした。天皇賞を勝ったときもまだ夢にすぎませんでしたが、宝塚記念で優勝してから現実的な計画になりました」。
あまりにも長く探求が続いており、できれば早く実現したいという話ではもはやない。しかし、ひょっとすると今年こそ、日本の前進と執念が報われる年になるのかもしれない。
By Peter Thomas
[Racing Post 2022年9月28日「'It was a terrible moment' - the holy grail that has brought 23 years of hurt」]